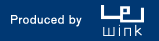眼鏡とコンタクトレンズの度数換算
多くの場合、コンタクトレンズと眼鏡の度数は違います。インターネットでコンタクトレンズや眼鏡を購入する場合は、とくに気を付けたほうが良いでしょう。
また、使用しているコンタクトレンズの度数から、眼鏡の度数をだいたい換算できることができます。
-3.75より低い度数を使っている場合、基本的には、眼鏡とコンタクトレンズは同じ度数を使えば良いといわれています。
しかし、度数が-4.00を超える場合は、「度数換算表」を参考に度数を換算します。度数換算表は、主に眼鏡店や眼科において検査員が参考にするものですが、インターネットで検索すると見つけることができますので、興味のある方は探してみてください。
また、どうしてコンタクトレンズと眼鏡の度数が異なるかというと、コンタクトレンズは眼球にくっついていますが、眼鏡は目から12mm~14mm程度離れているためです。コンタクトレンズの度数が-4.00を超える場合は、それより強い度数の眼鏡を作らないと、同じような見え方にはなりません。
たとえばコンタクトレンズの度数が-5.50の場合、眼鏡の度数は-6.00となります。コンタクトレンズの度数が-8.00の場合は、眼鏡の度数は-9.00となります。
乱視などの兼ね合いや目の形によって一概には言えない場合もありますので、眼鏡店や眼科で、きちんと検眼してもらってから眼鏡やコンタクトレンズを購入することをおすすめします。
サングラスの寿命を延ばす正しいお手入れ方法
サングラスのお手入れ、きちんとしていますか?屋外で使うことの多いサングラスは、一見汚れていないように見えても、汗や皮脂、砂、花粉などが付着しているんです。ここでは、サングラスの正しいお手入れ方法を紹介します。
まず初めに、サングラスの汚れを水で流しましょう。水で流さず、乾いた状態のレンズをクロスで拭くと、目には見えない微細な砂などでレンズを傷つけてしまう恐れもあります。蛇口からの流水で洗ってOKですが、フレームに負荷がかからないように水量は少なめに。
汚れが強い場合には、メガネ・サングラス専用のレンズ用洗剤を使って、汚れを落としていきます。洗剤を使った場合には、しっかり水ですすいでくださいね。汚れが落ちたら、タオルやティッシュペーパー、メガネ拭きなどを使って、サングラスに残った水気をキレイに拭き取るだけ。レンズだけでなく、フレーム部分もよく拭きましょう!
仕上げには、レンズクリーナーや曇り止めをお好みで。これらのケアアイテムを利用すると、帯電防止効果を付加でき、埃が付きにくいサングラスになりますよ。
サングラスのお手入れはとても簡単です。汚れを拭き取る前に、水でゴミを流すひと手間を加えるだけで、サングラスの寿命を延ばすことができるんですよ。クリアな視界を保つためにも、定期的にお手入れするようにしましょう!
ゴルフ用サングラスの選び方!正しく選んで快適にプレーを楽しもう!
長時間屋外でプレーをするゴルフでは、目を紫外線や砂埃などから守るためや、プレー中の眩しさを軽減するために、サングラスを取り入れるのがおすすめです。
ゴルフ用のサングラス選びでは、なるべく紫外線カット率が高いものを選びましょう!より快適にプレーをするためには、偏光レンズがおすすめ。偏光レンズは、太陽光の乱反射によるギラつきを抑えてくれるため、長時間のプレーでも目が疲れにくい優れもの。遠くまでハッキリ見えるので、芝目の見極めがしやすくなるという効果にも期待できます。
それから、レンズのカラーにも注目です。サングラスには様々なカラーがありますが、ゴルフで使うならブラウン系やピンク系を選ぶのがベスト!空や芝の色に似ているブルーやグリーンのレンズだとボールを見失いやすいため、避けるのが無難。また、薄めの色を選ぶのもポイント。「眩しさを軽減するには、暗いレンズの方がいいのでは?」と思うかもしれませんが、実はそれは間違いです。色の濃いレンズを使うと、瞳孔が開きやすくなり、より多くの紫外線を目に取り込んでしまう可能性があります。
ゴルフ用のサングラスは数多く発売されているため、ご自分のプレースタイルに合ったものをじっくり選んでみてください。サングラスを正しく選べば、芝目やボールを見やすくなり、スコアアップにも繋がるかもしれませんよ。
乳幼児の眼鏡
子供の視力が良好そうに見えていても、眼精疲労や根気が続かないなどの症状が出ているようであれば、眼科での屈折検査をお勧めします。近くが見えにくい遠視の場合、軽度であれば遠くの見え方に支障がないことが多いので、親が子供の屈折異常に気がつくことはなかなか難しいです。
生まれてから5歳~6歳までの乳幼児の時期は、視機能の成長にとって大変重要であるといわれています。もしこの時期に、遠視などの屈折異常が認められた場合は、視力を発達させるための治療として、眼鏡の装用が必要になります。治療せずそのままにした場合、弱視になりやすいといわれています。弱視とは、眼鏡やコンタクトレンズなどで矯正しても、視力が出にくい屈折異常のことです。
乳幼児は眼鏡の装用を嫌がる場合も多いですが、好きな色やデザインのフレームを選ばせるなどして、子供自身が気に入る眼鏡を作ってあげられると良いでしょう。
あまり知られていないことですが、弱視等の治療用眼鏡の作成には、「療養費」と呼ばれる補助金が出ます。加入している保険組合に申請すると、眼鏡の購入費用に対して補助を受けることができます。詳しくは自治体のホームページや、行きつけの眼科に問い合わせてみてください。
遠近両用メガネの慣れ方
遠近両用メガネの装用には、“慣れ”が必要です。快適に使えるようになるために、遠近両用メガネを購入したら、以下のような装用練習をオススメします。
まず、遠近両用メガネを座りながら使ってみることをお勧めします。手元においた雑誌や新聞などを読んで、次にテレビを観る、というような視線の移動を練習して、レンズの見える部分を確認してみてください。
次に、自宅などの慣れた室内で、立ち上がって使ってみましょう。自然な視線で見たとき、足元がぼやける感じがすると思いますが。これが遠近両用レンズの特徴です。
次に、メガネをかけて階段の上り下りをしてみましょう。ゆっくり足元をみながら階段を上ってみて、大丈夫そうなら足元を見ずに上ってみます。上りが問題なければ下りも行ってみましょう。
最後は屋外で試してみましょう。まずは歩きながら見え方を確かめます。完全に慣れるまでは、自転車や自動車の運転などは危ないので避けたほうが良いでしょう。
上記のような装用練習を通して、焦らずゆっくりと一か月くらいかけて、遠近両用メガネの装用に慣れていくことをオススメします。一か月使ってみても慣れないようなら、購入したメガネ店で相談してみてくださいね。
紫外線の脅威!冬こそサングラスを使うべき理由とは?
サングラスは夏のアイテムというイメージを持っていませんか?目の健康を考えるなら、冬にもサングラスを使うのがおすすめです。
冬は夏に比べると紫外線量は少なくなっています。しかし、それでもピーク時の半分くらいの紫外線が降り注いでいるんです!しかも、冬の紫外線はガラスを透過するUV-Aが夏に比べて多くなっています。そのため、家や車の中にいても油断は禁物となっています。
それから、UV-Aは波長が長いため、約90%が角膜を通過し、水晶体に吸収されやすいという特徴があります。水晶体に紫外線によるダメージが蓄積されると、白内障など目のトラブルを引き起こしやすくなるので、注意が必要です。
さらに、夏より冬の方が目に紫外線が入りやすいということも忘れてはいけません。夏場は高い位置から頭頂部に向けて紫外線が降り注いでいます。しかし、冬は太陽の位置が夏よりも下がり、目に光が届きやすくなります。そのため、夏よりも冬の方が眩しさを感じやすく、紫外線の影響を受けやすくなっています。
冬は、夏に比べて紫外線対策を怠りがち。しかし、健康な目の状態を保つためには、冬こそサングラスで紫外線対策を行うようにしてみてください。
雪山での目の日焼け!「雪目」を防ぐサングラスの選び方
スキーやスノーボード、そんな雪山でのアクティビティに欠かせないのがサングラス。なぜ雪山でサングラスが必要なのでしょう?
目に強い紫外線を浴び続けると、角膜が傷ついてしまいます。これが「雪目」と呼ばれる状態。紫外線を浴びた数時間後に、目に痛みを感じたり、眩しさを感じたり、涙が止まらなくなったり、といった症状がみられます。
そんな雪目になりやすいのが、雪山です。なぜかというと、真っ白な雪の地面は紫外線を反射してしまうから。その紫外線量は、太陽から直接降り注ぐ紫外線と地面からの反射される紫外線を合わせると、市街地の2倍にもなると言われています!
雪目を防ぐためには、サングラスを利用するのが有効です。サングラスを選ぶ際には、必ず紫外線カット率が99%以上のレンズを選びましょう。さらに偏光レンズであれば、雪面からのギラギラとした反射光を防いでくれるため、目への負担を軽減できます。それから、サングラスの形状も大事なポイント。顔の形にフィットするものをチョイスすることで、隙間からの紫外線の侵入も防ぐことができます。
雪目は、雪の中にほんの数分いただけでも発症してしまう可能性のある病です。雪山に限らず、雪の多い地域にお出かけの際には、サングラスの用意を忘れないようにしましょう!
2021年 メガネとマスクのお悩み解決
マスクをするのが当たり前となった今。
メガネを掛けてマスクをすると曇ってしまう、耳が痛くなってしまうなど、悩みは尽きません。
寒くなってきて、より一層、曇りやすくなってくるこの季節。
少しでも曇りを解消したいと思いますよね。簡単にメガネを曇りにくくするグッズや、マスクで耳が痛くなってしまうのを軽減するグッズが、眼鏡店さんで販売されているのをご存知ですか?
メガネが曇って困るという方にはコレ!!
■ジェルタイプの曇り止め(アンチフォグ)

今お使いのメガネのレンズの両面〈表裏〉に米粒程度のジェルを塗り、指先で伸ばしてから、ティッシュや柔らかい布でジェルが残らないようにしっかりと拭き取ってください。1回塗るだけで、くもり止め効果が長時間持続します。
また、コンパクトサイズなのでバックなどに入れて持ち歩くことも出来て便利です!
その他にも液体タイプのものやメガネ拭きのタイプなどもあるので、眼鏡店さんにご相談してみてください。
マスクとメガネで耳が痛くなってしまうという方にはコレ!!
■首下で使うマスクフック(マクピタ)


マスクを耳ではなく、首すじや首下または後頭部で留めて長時間マスクを掛けている時の耳の痛みを軽減します。
この蟹のような形状は、マスク紐の取り付け方により弱・中・強と長さ調整が可能になるように考えられています。
素材にもこだわっていて、ほ乳瓶などにも使用されている柔らかくて人体に安全な「エラストマー樹脂」を使っているので安心してお使い頂けます。
その他にもメガネのツルの先端に付けるタイプなどもあるので眼鏡店さんにご相談してみてください。
マスクをする時のちょっとした工夫も別の記事でご紹介をしました。合わせて読んでみてください。
『マスクによるメガネの曇りを解消!着用のコツや便利アイテムを紹介』
http://meganeand.jp/lifestyle/2020-8-9-anti-fogging-1/
ブルーライトカットメガネで、目の疲れが軽減できるって本当?
パソコンやスマホの画面から発せられるブルーライトは、目の疲れや視力低下の原因の1つ。そう言われるようになってから、多くのメーカーからブルーライトカットメガネが発売されました。
しかし、実際のところブルーライトカットメガネに目の疲れを軽減する効果はあるのでしょうか?
実は、ブルーライトカットメガネの効果が実感できるかどうかには、個人差があります。
「ブルーライトカットメガネを使用したら、目の疲れや肩こり、頭痛が軽減した」という人もいれば、「あまり効果を感じなかった」という人もいます。
しかし、「効果が実感できなかったからブルーライトカットメガネは意味がない」ということではありません。
2014年に神奈川県で行われた『ブルーライトメガネの透過率テスト』によると、ブルーライトメガネには13.3%~57.5%のブルーライトカット効果があることが実証されています。
ブルーライトが目に与える影響は、ハッキリと解明されているわけではありません。
しかし、身体に悪影響を及ぼす可能性が少しでもあるのなら、早いうちから対策しておくのがよさそうですね。特に、パソコンやスマホに触れる時間が長い人は、ぜひブルーライトカットメガネを取り入れてみてください。
100円ショップでも買える!?ブルーライトカットメガネの選び方
ブルーライトが目に与える影響を手軽に軽減できるのが、ブルーライトカットメガネ。
パソコンやスマホを長時間使用することが多い現代社会では、ぜひ取り入れたいアイテムですよね。今回は、ブルーライトカットメガネ選びの2つのポイントを紹介します。
1.タイプで選ぶ
ブルーライトカットメガネは「反射タイプ」と「吸収タイプ」に分けられます。
「反射タイプ」は、レンズが透明なので普段使いにピッタリ。しかし、ブルーライトカット効果は低めです。
「吸収タイプ」は、ブルーライトカット効果が高いので、一日中デスクワークをする時におすすめ。ただ、レンズに薄茶色や青色などのカラーが入っているので、普段使いはしづらい、という面があります。
2.ブルーライトカット率で選ぶ
ブルーライトのカット率は、周りの環境や作業内容に合ったものを選ぶのが大切です。
ブルーライトをカットしすぎてしまっても、疲れ目の原因となってしまうことがあります。明るい環境で使うなら、カット率はJIS規格で40%くらいあれば十分。暗い場所なら、80%くらいのものを選ぶといいですよ。
最近では、ブルーライトカットメガネは100円ショップでも取り扱われています。
手軽に手に入るようになった分、きちんと効果のあるものを選択して使うようにしましょう。
先手必勝⁉花粉から目を守ろう!
スギ・ヒノキ…このワードを聞いただけでなんだか憂鬱…
花粉症の方にとっては嫌な季節がだんだんと近づいてきました。
地域にもよりますが、早いところだとスギ・ヒノキの花粉は1月末から飛び始め、GWくらいまでが飛散のピークです。
2021年の飛散量予想として、一部の地域を除きほぼ全国的に前年よりも多い(‼)とのこと。東京は前年の3倍なんて予想も(恐ろしい…)
筆者も毎年悩まされている花粉症。ほんの3、4年前まで花粉症なんてまるで他人事でしたが、ある日あまりの目の痒さに我慢が出来ず眼科に駆け込んだ日から、つらい花粉症との闘いが始まりました(ちょっと大袈裟!?)
同じように、花粉症は誰がいつ発症するかわかりません。
毎年悩んでいる人も、ちょっとムズムズするかもという予備軍の人も。
ぜーんぜん平気!という羨ましい方も。目に見えにくい花粉だからこそ、症状が出る前にしっかり防いで、早め早めの対策を取って行きましょう。

さて花粉症の症状といえば、鼻のムズムズや肌荒れもつらいですが、筆者は何より目の痒さが酷く、ピーク時はいつも充血、目のまわりの肌はヒリヒリ状態でした…。
そのため、普段はコンタクトレンズを使用していますが、花粉シーズンはメガネに換えるようにしています。
その理由として、コンタクトレンズが汚れていると花粉が付きやすいということをご存じでしょうか?
レンズ汚れの主な原因は涙液(涙)に含まれるタンパク質や脂質。これがレンズに付着し、汚れとなります。このタンパク質や脂質は吸着性があるため、レンズが汚れることによってさらに花粉が付きやすくなってしまいます。
また、かゆみで目をこすると粘膜が傷ついて、細菌による充血や結膜炎を引き起こす恐れも。
コンタクトレンズを常に清潔にしておくことも大切ですが、メガネにすることで花粉を引き寄せてしまうリスクを減らすことができます。
ゴーグルタイプのメガネがなくても、普段使っているメガネで目に入る花粉の量は減らせます!
花粉や塵を寄せ付けない帯電防止のレンズコートもあるので、お近くの眼鏡屋さんで聞いてみて下さい。
(マスクをするとメガネが曇って困る…という方向けに、曇りにくいコートや曇りを防止するアイテムも沢山ありますのでこちらも気軽にご相談下さい!)
帰宅後はうがい・手洗いと同時に目も洗いましょう!
(目専用の洗浄液を使ったり、目薬をさすのもGOOD!)
それでも目がかゆいなと感じたら、こすらずに水で濡らしたタオルでまぶたを冷やすとかゆみが落ち着きますよ。
厄介な花粉から目を守って快適な春を一緒に迎えましょう🌸